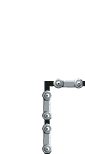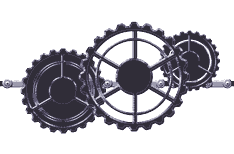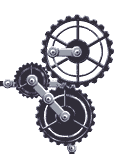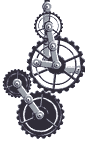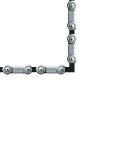「雨…やまないね」
「……」
追いかけて来た、黒い影はもう見えない。
この大雨の中、
生憎開店している店を近場に見つけられず、
仕方がなく私達はバリケード下で固まっていた。
「寒い?あ、買ってきたスープあるんだけど一緒に」
「…触らないで……」
か細く、だが、強く、相手を避ける。
そうだ、彼女は、あの時の、
そして、彼女も、恐らく、私のことを、気付いている、
お願い、こんな、弱い、私を、
「…やっぱり、あの時私を助けてくれた人よね?」
「……」
ビクリ、と僅かに肩が震える。
無言の肯定。
それに彼女は小さく笑う。
馬鹿にする気?
被虐AAのくせに…弱い…私より…ずっと弱いくせに…!
「ずっと、言いたかった事があって」
やめて、どうせ、嘲るんでしょ…こんなに…弱い私を
「この前は…その」
やめて!やめて!
「…ありがとう」
「……え?」
虚を突かれた、正にそんな表現どおり、
私はキョトンを顔を上げる。
「あの時は有耶無耶で、
適当にお礼を言っちゃったみたいだし」
「ま、待って…」
礼を言われる筋合いはない。
「え?」
「だって…私…酷い事を…い、言った…のに。
…こ、ろすって…」
「あ、うん。それはやっぱり驚いたけど」
ケラケラと彼女は笑う。
「でも、その時の目がね、
凄く辛そうで、悲しそうで、
…あ、思わず口から出ちゃったのかな?…って思って」
「……なん、で」
「ごめん。えと、私の勘違いだったら恥ずかしいけど。
…でも、ええと、こんな時にだけど、会えて良かった」
「……そんなの…変」
「変?」
「だ、だって」
声が上ずる。
「だ、大体…怖くないの?…私は、虐殺AAで、あなたは、」
「被虐AA、だから?」
クスリ、と彼女は笑う。
「そういう風に分ける方がおかしいのよ。
まるで白人はエライ、黒人はワルイ、ってなこと言ってる
昔の馬鹿な人みたい」
「馬鹿…」
思っても見なかった答えに、私は言葉をなくす。
「あ、違う違う!
あなたを馬鹿とか言ってる訳じゃなくて…その…それは、
いつか私も、虐殺されるかもしれないけど…けど、
それに怯えてビクビクしているって変だと思う。
可能性をまるっきり捨てちゃって、自分から殺して下さい、
って言ってる様なものじゃない」
「可能性…」
ぼんやり、その言葉を反芻する。
「ま、できる事は色々やってみたいしね。
間違ちゃったら間違ったで、もう必死で謝ってみたり。
…そんな状況なりたくないけど」
ペロリ、と舌を出して軽く彼女は笑む。
信じられない。
まるで。
私は、彼女の顔をマジマジと見つめる。
「変だと思ってる?」
「…凄く」
「やっぱり思うよね。
…でも、どうにもならない人生って分かっていて
いずれ死ぬって分かっている。
だったら、好きな事をしない方が…よっぽど変じゃない」
「……でも、」
「…ねぇ、それより」
「え?」
「私は、あなたの事、聞きたいな」
「私のこと?」
「…死にたがってたでしょ、さっき」
「………」
僅かに、顔を伏せる。
「別に、死にたくなる時は何度もあるけど、
そこで、思い直さなきゃ駄目じゃない、だから」
ニコリ、と優しく彼女は笑う。
「恥ずかしいとか思わないで、
ココにつっかえているモヤモヤ、吐き出したらいいのよ。
…きっと、話し終わった頃に、気持ちは晴れているから」
トン、と私の胸を指し、彼女は優しく言う。
…瞳が、けして野次や面白半分ではないことを、
物語っていた。
「私は……」
「大丈夫。
…逆に、知らない人、これから先、もう会わない人に言うんだ、
って考えればいいのよ?」
優しい、魔法の声。
「あ、それとも先にスープを飲む?」
思い出したように、彼女は私にカップスープを手渡す。
買ったばかりだったのだろうか、
暖かく、手に、じんわりと、しみこんでいく。
「あの…」
「ほら、冷めないうちに」
「……すみません…」
コクリ、と私は一口スープを飲む。
温かく、暖かい。
優しさが、胸に痛い。
嗚呼
あんなに、
酷いことを言ったのに、
こんなに、
やさしくされる、
資格なんてないのに、
ひとりでに、頬を、涙が伝った。
――― 12 ―――